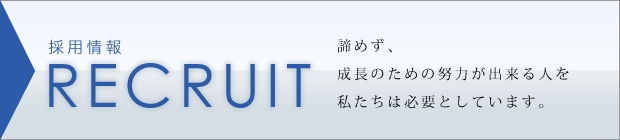最新情報WHAT'S NEW
年末調整のしかた
『平成24年分 年末調整のしかた』が、国税庁のホームページに公開されています。
昨年との変更点としましては、次の事項になります。
(1)生命保険料控除の改組
①平成24年1月1日以後契約(新契約といいます)と、平成23年12月31日以前契約(旧契約といいます)で、控除額が変わります。
適用限度額は、一般、個人年金保険料それぞれ、新契約が4万円、旧契約が5万円となります。
②新契約については、従来の一般、個人年金保険料控除に加え「介護保険料控除」が新設されます。
適用限度額は、4万円となります。
③生命保険料控除は、最大で12万円となります。
※一般又は個人年金に新契約と旧契約が両方ある場合、保険を転換した場合など、注意が必要となります。
(2)納期の特例の適用を受けいる源泉徴収義務者の、7~12月に徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日までになりました。
(3)マイカー通勤者などが受ける通勤手当の非課税限度額が、通勤距離比例額までに縮小されました。
詳しくは、こちらまで
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm
納税環境整備に関する国税通則法等の改正について
納税環境整備に関する国税通則法の改正を含む「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が、平成23年11月30日に成立し、同年12月2日に公布されました。
この改正により、調査手続の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続について現行の運用上の取扱いが法令上明確化されるとと もに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由附記の実施及び記帳義務の拡大等が定められ、税務調査手続の法定化及び理由附記の実 施に係る規定については、平成25年1月1日から施行することとされています。
また、税務調査手続について、一般の納税者の方や税理士の方を対象とした質疑応答集(FAQ)を作成しました。
税務調査手続き等の先行的取組の実施について
法定化された税務調査手続等は、原則として、平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されることとなりますが、国税庁では、法施行後における税務調 査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、平成24年10月1日以後に開始する調査から、法施行後に実施することとなる一部の手続について、先行的に取 り組むことを予定しています。
更正の請求期間の延長等について
今般の改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が原則として法定申告期限から5年に延長されました。
処分の理由附記について
今般の改正により、処分の適正化と納税者の予見可能性を高める観点から、原則として、平成25年1月1日以後、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分や不利益処分を行う場合には、理由附記を実施することとなります。
(国税庁HPより抜粋)
中小企業経営力強化支援法
中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)が8月30日より施行されました。
税理士や金融機関など中小企業の支援事業を行う者を認定し、中小企業に対して専門性の高い支援を行い、その活動を後押しすることが目的です。
平成25年3月で中小企業金融円滑化法が期限を迎えることから新たな中小企業支援措置として注目が集まっています。
くわしくはこちらから↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2012/0830Kaigai-kaisei.htm
消費税法の一部を改正する等の法律案が可決・成立
参議院本会議において8月10日、「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律案」が可決・成立しました。
これにより消費税率が、平成26年4月1日に現行の5%から8%に、平成27年10月1日に10%に、2段階で引き上げられることになります。
また、新たに設立される法人のうち大会社の関係会社で、グループ内のいずれかの法人の課税売上高が5億円を超える等、一定の要件を満たすものは、基準期間がない事業年度においても納税義務が免除されないこととなります。
他にも工事請負契約に改正前の税率を適用する経過措置などが盛り込まれた法案となっています。