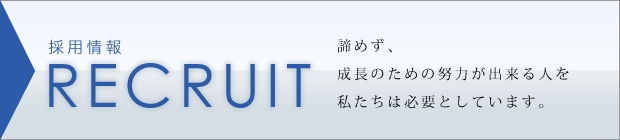最新情報WHAT'S NEW
年金制度改正法が成立 106万円の壁を撤廃
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律が6月13日、参議院本会議で可決、成立されました。当初の法案に自民、公明、立憲民主の3党による「将来の基礎年金の給付水準の底上げ」に係る修正案が盛り込まれています。
日本の公的年金制度は、2階建てとなっています。1階部分は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する基礎年金(国民年金)、2階部分は、一定規模以上の会社等に勤務している人が加入する厚生年金です。基礎年金と厚生年金には、それぞれ「マクロ経済スライド」という措置が講じられています。マクロ経済スライドとは、賃金と物価による元々の改定率に被保険者の減少や平均寿命の延び等に応じて調整を加え、保険料等の収入と年金給付等の支出の均衡が保たれるよう、時間をかけて緩やかに年金の給付水準を調整する仕組みをいい、平成16年の年金制度改正で導入されました。
現行において、基礎年金のマクロ経済スライドに係る終了時期と、厚生年金のマクロ経済スライドに係る終了時期の見通しに著しいズレが生じています。これにより基礎年金の給付水準が低下するおそれがあるといいます。
改正後は、次期財政検証において、両者の終了時期の差異により、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合、基礎年金のマクロ経済スライドと厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させるため、必要な法制上の措置を講ずることとしました。
同時終了すると、基礎年金の給付水準低下を抑えることができます。同時終了の手段として、厚生年金の積立金を利用することが検討されるといいます。
また、同時終了した場合における基礎年金と厚生年金の合計額が、同時終了しなかった場合の合計額を下回るときに対する配慮措置も置かれています。
基礎年金の底上げ以外の改正項目については、当初法案と同様です。厚生年金・健康保険に係る短時間労働者の加入要件の見直しとして、賃金要件は公布から3年以内の政令で定める日から撤廃され、企業規模要件は令和9年10月1日から段階的に撤廃されます。賃金要件の撤廃により、いわゆる「106万円の壁」は解消されることとなります。
査察の概要
国税庁から令和6年度の査察の概要が公表されました。
査察は7,悪質な脱税者に対して刑事責任を追及する制度です。
適正・公平な課税の実現を目指し一罰百戒の効果を期するものです。
令和年6年度の告発軒数は98件、告発額は82億円に達しています。
経済取引の広域化、デジタル化、国際化による脱税手段の複雑、巧妙化への対応が求められています。
令和6年度中のされた一審判決99件すべてに有罪判決が言い渡され、13人に対して実刑判決が下されています。
詳しくは国税庁 査察の概要 まで。
m
国税庁 防衛特別法人税の申告書様式の情報を公開
国税庁は、5/30日、令和7年度税制改正で創設された「防衛特別法人税」の申告書様式等に係る情報を公表しました。原則すべての法人に申告義務が生じる防衛特別法人税の申告書は、法人税及び地方法人税等(以下「法人税等」)の"次葉"として追加されることなどが示されています。
令和8年4月1日以後開始事業年度の法人税等の申告では、防衛特別法人税額がない場合でも別表一の本体と併せて、別表一次葉一の防衛特別法人税額の欄等に「0」と記載して提出する必要があります。防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算します。
前述の通り、防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額500万円を控除するため、納付する税額が生じない可能性があります。
しかし、基礎控除額500万円の控除により課税標準法人税額がゼロの法人や赤字等により基準法人税額がゼロの法人であっても、防衛特別法人税の申告は必要となります。つまり、収益事業を行っていない公益法人などの法人税の納税義務のない法人等を除き、すべての法人について申告義務が生じることになり、防衛特別法人税の確定申告書は、原則、事業年度終了日の翌日から2か月以内に所轄税務署長に提出することになります。
国庫への帰属が認められた土地
2023年4月27日より施行された相続した土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属法の運用状況に関する統計の速報値が法務省のホームページに公開されました。
「相続土地国庫帰属法」(正式名称:相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)とは、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた法律で、相続または遺贈によって、宅地や山林、農地などの土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
運用状況によると、令和7年4月30日現在における申請件数(総数)は3732件となっており、地目別にみると田・畑が最も多く1431件、宅地1302件、山林582件、その他417件だった。
このうち、帰属が認められた件数(総数)は1586件。種目別にみると、宅地が603件と最も多く、農用地497件、森林89件、その他397件。
一方で却下件数は58件で、却下の理由としては、「現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1項)に該当」が12件、「境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当」が11件、「法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)」は33件などでした。
この他、取下げ件数は604件。原因は自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した。隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった。
法務省の該当ページはこちら