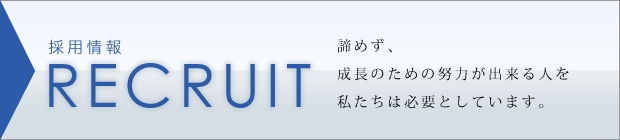最新情報WHAT'S NEW
紙の手形・小切手は 2026 年度末まで
政府・産業界・金融界が協力し、手形・小切手機能を2026年度末までに全面的に電子化することを目指しています。
紙の手形・小切手を使われている方は、2026年度末までに以下手段に切り替える必要があります。
①現預金での支払い
②電子記録債権(でんさい)による支払い
でんさいは、印紙代、郵送料の削減、盗難リスクの削減等からも紙の約束手形に比べメリットがあります。
手形や小切手での支払いがある場合は、取引先と支払い条件の変更等を調整し、必要に応じ契約の更新等を行います。取引先が支払いに手形や小切手を利用している場合は、今後の予定を確認しておきましょう。
全国銀行協会 手形・小切手利用廃止のチラシはこちら
金融機関の手形・小切手の発行終了と全面的な電子化に向けての対応について
静岡銀行はこちら
富士宮信用金庫はこちら
富士信用金庫はこちら
中小経営強化税制に係る手引き等を公表
中小企業庁より中小企業経営強化税制に係る手引き等が公表されました。
「経営力向上計画策定の手引き」、「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」の2点は、令和7年度改正等を踏まえて改訂されました。同改正で見直された生産性向上設備(A類型)及び収益力強化設備(B類型)や、創設された経営規模拡大設備等(E類型)に係る適用要件の内容等が示されています。
「中小企業等経営強化法の経営力控除設備等のうり経営規模拡大設備等(E類型)に係る経済産業大臣確認の取得に関する手引き」は、新たに公表されたもので、E類型の手続きスキーム等が図で示されています。
中小経営強化税制に係る手引き等は、こちら をご覧ください。
令和7年分の路線価等が公開されました
令和7年7月1日に、国税庁より令和7年分の路線価が公開されました。
相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。
土地等の時価を個人が把握することは困難であるため、国税庁では毎年全国の民有地について、土地等の評価の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
路線価等は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定めています。
路線価等は、1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定めています。
前年と比較して、全国平均2.7%上昇しています。4年連続の上昇となります。
都道府県の最高路線価が上昇した都市は、35都市を数えます。
全国の県庁所在都市の最高路線価は、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りで、1㎡当たり4,808万円です。
静岡県の最高路線価は、静岡市葵区紺屋町名店会呉服町通りで、1㎡当たり118万円です。
国税庁では平成30年から令和7年までの路線価等を公開しています。詳しくは 国税庁 路線価 まで。
退職所得の源泉徴収票 従業員分の提出について
令和7年度改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が“法人の役員である居住者”から“すべての居住者(役員・従業員等)”に見直されたため、改正後は源泉徴収義務者(支払者)は、従業員分についても所轄税務署長と市区町村長に提出する必要があります。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、原則として、退職手当等を受給する者の退職後1ヵ月以内に、支払者は受給者に交付することに加え、所轄税務署長、市区町村長(支払年の1月1日現在の受給者の住所地)に、それぞれ1枚ずつ提出する必要があります。
現行では、所轄税務署長に提出する「退職所得の源泉徴収票」については、例外として、その年中に退職した受給者分を取りまとめて、翌年1月31日までに提出できる取扱いが設けられています。この取扱いを適用すれば、支払者は、役員が退職する度に所轄税務署長に提出する必要はなく、1年分をまとめて提出することができます。改正後も、同取扱いは存続するため、支払者はその年中に退職した全ての居住者に係る同源泉徴収票をまとめて、翌年1月31日までに提出すればよいということになります。
従業員分も所轄税務署長、市区町村長に提出が必要となるのは、「令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等」に係る同源泉徴収票等からとなります。このため、所轄税務署長への取りまとめ提出の取扱いを適用する場合、令和7年と令和8年以後で取りまとめる対象が異なります。
年末時点の未払退職金に注意が必要です。従業員に対する退職手当等の支払が令和8年1月1日以後にされる場合であっても、退職手当等が令和7年末の時点で“未払い”となっていた(退職手当等は令和7年分の退職所得に該当する)場合は、従業員に係る同源泉徴収票等を所轄税務署長等に提出する必要はないとのことです。