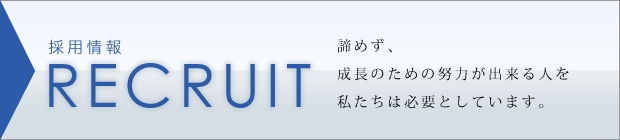最新情報WHAT'S NEW
ペイオフによる損失に係る税務
先日、日本振興銀行の破綻を受け、預金保険機構はペイオフを実施しました。
ペイオフで保護されるのは普通預金や定期預金などの場合は元本1千万円とその利息までで、これを超える部分の預金は保護の対象外となります。
ペイオフが実施され、保護されない部分の預金が戻ってこない場合は預金者は損失計上することになります。
この損失について、税務上救済措置があるのでしょうか。
結論から申し上げますと、法人の場合は損金になりますが、個人の場合は控除されません。
雑損控除の適用が考えられますが、、事業用資産や山林、生活に通常必要でない資産について受けた損失は対象とならず、詐欺や脅迫による損失も対象とはならないとされています。
1,000万円を超えるお金は全額保護される当座預金等の決済性預金に変えるのも一つの手かなと思います。
小規模宅地等の記載例を公表
国税庁は、このほど「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る相続税の申告書の記載例等について」をHP上で公表しました。
複数の利用区分が存在する場合等下記の9つの例について、申告書記載例を示しています。
(平成22年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した小規模宅地等について適用を受ける場合の記載例になります。)
平成22年度の税制改正で、相続発生後、相続人が事業や居住を継続できるように小規模宅地等について相続税の課税の特例が制定されていましたが、その制度趣旨をより徹底する為に、事業や居住を継続していない場合には適用対象から除外する等の見直しが行われています。
・複数の利用区分が存する場合
・被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸付事業の用に供されていた場合
・特定同族会社事業用宅地等と貸付事業用宅地等が混在する場合
・マンションの区分所有権の数戸を取得した場合
・共有宅地についての小規模宅地等の特例の選択
・共同住宅の一部が空室となっていた場合
・申告期限までに宅地等の一部の譲渡があった場合
・被相続人等の居住用宅地等を共有で取得し、その1人に小規模宅地等の特例の適用がある場合
・店舗兼住宅の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けていた場合
詳しい内容はこちらになります。
国税庁HP
住宅エコポイントに係る税務
住宅エコポイントの申請が3月からスタートしました。
上記制度は、平成22年12月31日までに着工し、一定の基準を満たした住宅を新築した場合一戸当たり一律30万ポイント(1ポイント=1円)が、リフォームを実施した場合にはその工事の種類に応じて最大で30万ポイントが発行されるというものです。
ポイントの利用方法については、省エネ・環境配慮に優れた商品や地域振興券、商品券やプリペイドカード等と交換や追加工事の費用に充当が挙げられます。
税務上の取扱いですが、法人又は個人事業者の事業にかかるポイントの場合は、ポイント利用時に雑収入に計上することとなり、一般の個人にかかるポイントの場合はポイント利用時に一時所得として税金の計算を行うこととなりますのでご注意下さい。