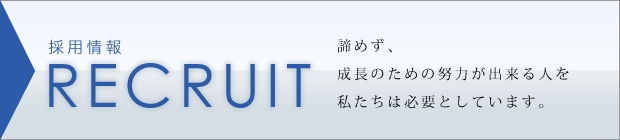最新情報WHAT'S NEW
個人の暗号資産取引における申告手続きについて
代表的な暗号資産であるビットコインの高騰により、多額の含み益が生じているケースがあるようです。暗号資産取引では、マイニングやステーキング等による取得を除き、保有する暗号資産の売却や使用、交換等により実現した利益が所得税の課税対象となります。
保有する暗号資産を売却した場合であれば、その暗号資産の譲渡価額と譲渡原価等の差額が損益となり、その所得は原則として「雑所得(その他雑所得)」に区分されます。
だだし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合で、暗号資産取引に係る帳簿書類の保存ががる場合は原則として「事業所得」に、帳簿書類の保存が無い場合は原則として「雑所得(業務に係る雑所得)」に区分されますが、収入金額300万円超や帳簿書類の保存の有無は、あくまで外形上の例示に過ぎないため、営利性が認められない等、個々の状況によっては、所得区分に関する過去の判決内容等を踏まえ、その該当性を判断する必要があります。
また、暗号資産の法定評価方法は、総平均法ですが、所得税の暗号資産の評価方法の届出書を提出することで移動平均法による計算も可能です。
なお、「雑所得(業務に係る雑所得)」を有する場合は、その収入金額に基づき一定の対応が必要となります。
その年の前々年分の収入金額が300万円超の場合は、申告対象年の「現金預金取引等関係書類」(業務に係る雑所得に関して作成・受領した請求書や領収書等のうち、現金の収受や払出し等に際して作成されたもの)の保存が必要となります。
その年の前々年分の収入金額が300万円以下の場合は、業務に係る雑所得の金額の計算上、総収入金額や必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額及び費用の額とすることができる(いわゆる現金主義の特例)が、申告書に適用を受ける旨を記載する必要があります。
その年の前々年分の収入金額が1,000万円超の場合は、総収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書等の添付が必要となります。
国外財産調書の提出状況
国税庁より令和5年分の国外財産調書の提出状況が公表されました。
国外財産調書制度とは、居住者で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の6月30日までに所轄の税務署提出しなければならないという制度です。
総提出件数は 、13,243件 です。
総財産額は、 6兆4,897億円 となっています。前年から67億円増加しています。
種類別の財産総額のトップは有価証券で、総額4兆905億円、構成比63%となっています。
次が預貯金で、総額8,479億円、構成比13.1%です。
この2つの財産で、全体の75%を超えています。
詳しくは 国税庁令和5年度国外財産の提出状況 まで。
小規模宅地等特例~老人ホーム入所後の自宅建替え時~
小規模宅地等の特例とは、相続開始の直前において、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、土地の種類において評価額が減額される制度である。
被相続人が生前に老人ホーム入所後、同居親族が自宅を立て替えた場合の同特例の適用関係について、実務家の疑義が生じている。 被相続人の老人ホームの入所が長引き、その最中に自宅の老朽化等により、同居していた親族が自宅を立て替えた場合に、被相続人が相続開始の直前に居住していた自宅とは言えず、本特例を適用できないのではないかと疑問視する声もあった。
本特例は法令上において、相続開始の直前に被相続人等の居住の用に供されていた「宅地等」が対象であるため、被相続人が老人ホームに入所する前後で、居住していた自宅が物理的に全く同じ家屋であることまでは求めていないと解されるという。
また、自宅の建替え中で相続が開始する直前に被相続人が居住していなかった場合でも、被相続人はその自宅に居住していたものと同視して本特例の適用を認めるといった取扱いなどがある。
こうした観点から、老人ホーム入所後に自宅が建替えられ、その建て替え後の自宅に被相続人が居住しなかったとしても、その自宅の敷地は「相続開始の直前に被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に該当し、本特例の対象として認められるものであるという。
精算課税 令和5年改正後初の申告にあたっての留意点
・令和5年度改正で基礎控除を創設
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母など(特定贈与者)から財産の贈与を受けた18歳以上の子又は孫などの選択により、贈与税・相続税を通じて課税が行われる制度です。
令和5年度改正により、令和6年1月1日以後の贈与から基礎控除(110万円)が導入され、年間贈与額から基礎控除額、特別控除額(限度額2,500万円)を控除した残額に対して、一律20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。そして、特定贈与者の死亡時の相続税の計算上、精算課税適用財産の贈与時の価格から基礎控除額を控除した残額を相続財産の価格に加算します。
精算課税を初めて適用する場合に提出が必要な書類は、年間贈与額が基礎控除の110万円を超えるか否かで異なります。
年間贈与額が基礎控除の110万円以下の場合は、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」に受贈者の戸籍の謄本等一定の書類を添付して提出します。一方で、年間贈与額が110万円超の場合、贈与税の申告期限までに「贈与税の申告書」に「相続時精算課税選択届出書」等を添付して提出しなければなりません。