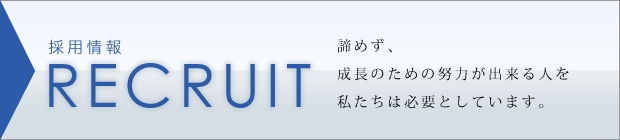最新情報WHAT'S NEW
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。
1 基礎控除の見直し
-
- (1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
- 合計所得⾦額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
- (1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
| (注) | 1 | 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。 |
| 2 | 合計所得⾦額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した⾦額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。 | |
| 3 | 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。 |
- (2) 基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。
2 給与所得控除の見直し
- (1) 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
- (2) 給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
3 特定親族特別控除の創設
-
- (1) 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適⽤を受けようとする⼈は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
- (1) 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
| (注) | 「特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。 なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。 |
- (2) 令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各⽉(⽇)の源泉徴収の際に適⽤されることとされました。
- 給与 : 親族の合計所得⾦額が58万円超100万円以下である場合
- 公的年⾦等 : 親族の合計所得⾦額が58万円超85万円以下である場合
4 扶養親族等の所得要件の改正
上記1⑴の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
- 扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
- ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
- 勤労学⽣の合計所得⾦額の要件 : 85万円以下(改正前:75万円以下)
また、上記2⑴の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
詳しくはこちらをご覧ください。
交際費 得意先を乗せたタクシー代のミスに注意
令和6年度改正により、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の基準が5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。
そもそも法人税における交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係ある者等に対する接待、供用、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。
ただし、「飲食費」については、交際費等の範囲から除かれており、一定事項を記載した書類の保存を要件に1人あたり1万円以下の金額まで損金算入できます。1人当たりの飲食費が1万円を超えた場合は、超過部分のみではなく、全額が交際費等となります。いわゆる1万円基準と呼ばれるもので、資本金の大小や、支配関係の有無などによる制限がないため、全法人が適用できる制度です。
ここでの飲食費等とは、交際費等のうち「飲食その他これに類する行為のために要する費用」(社内飲食費を除く。)とされています。具体的には、”飲食等”という行為をするために必要な費用で、飲食代のほか、テーブルチャージ料やサービス料など、飲食店等に直接支払うものが対象となります。
一方、接待等を行う飲食店等へ得意先を送迎するため自社が負担した送迎費は、テーブルチャージ料等の取り扱いと異なります。送迎費は、本来、接待等に当たる飲食等を目的とした”送迎”という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものではないため、飲食費に該当せず、「交際費等」に該当します。そのため、接待対象の得意先等を飲食店等に向かわせる、または、飲食店等から自宅等に帰宅させるための送迎タクシー代などは、「交際費等」に該当します。送迎タクシー代を合算して飲食費の1万円基準の判定をし、1万円以下なら合算額すべてを飲食費することはできないので注意が必要です。
iDeCoの令和7年度税制改正
2024年12月に勤務先への申請なしにiDeCoに加入できるようになり、企業年金と共済加入者の掛金上限額が引き上げられるなど改正があったiDeCoですが2025年も改正があります。
1、掛金上限額の大幅な引き上げ
・第1号被保険者(自営業者等)
掛金上限額が月額68,000円から75,000円に引き上げられました。
・第2号被保険者(会社員・公務員)
企業年金加入者 …月額2万円→月額 6.2 万円(他の企業年金と合算が上限)
企業年金未加入者…月額2.3万円→月額 6.2 万円
2、加入可能年齢の拡大
これまでは、iDeCoに加入し掛金を拠出できる期間は20歳から65歳までとなっておりました。今回の税制改正により、「iDeCoの加入者・運用指図者だった」または「私的年金の財産をiDeCoに移換できる」場合には、70歳未満まで引き上げられる予定です。
iDeCoは、掛金が全額所得控除になることや掛金の運用益が非課税であることから、節税効果のある制度になっていますが、掛金の負担や運用リスク、受け取り時の適切な選択といった課題は変わらず残ります。制度利用前にメリットだけではなくデメリットも考慮してiDeCoを利用するか考えていただければと思います。
103万円の壁の見直し 国会で成立
令和7年度税制改正法案が3月31日、国会で成立し、同日に公布されました。
いわゆる「103万円の壁」の見直しでは、給与収入200万円相当以下の者には所得税の基礎控除を47万円引き上げ、課税最低限が160万円となりました。この上乗せ措置は、恒久的措置とされています。なお、中所得層を含めた税負担軽減では、令和7年分及び令和8年分の措置として、税負担を軽減する対象を段階的に給与収入850万円まで引き上げられます。一方で、社会保険料がかかる106万円の壁は議論の途中で、働き控えを防ぐ効果ははっきりしていません。
納税が困難な場合の猶予制度
国税庁のホームページから、納税が困難な場合の猶予制度についてのお知らせがアップされています。
今般の物価高や、国際的な経済状況の不安定感からかと思われます。
国税の猶予制度としては、換価の猶予と納税の猶予が挙げられます。
換価の猶予は、国税を一時に納付することにより、事業の継続・生活の維持が困難となるおそれがある場合に、納税者からの申請により、延滞税が軽減される手続きです。
納税の猶予は、災害等を受けたこと、病気にかかったこと、事業につき著しい損失を受けた場合などに、納税者からの申請により、延滞税の免除又は軽減される手続きです。
いずれの場合にも申請が必要となります。まずは、所轄の税務署へご相談ください。
詳しくは こちら まで。