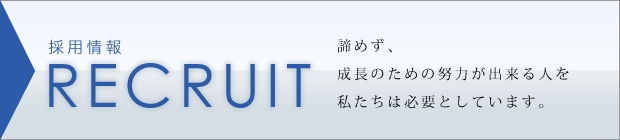最新情報WHAT'S NEW
ホステスの源泉所得税を巡って争われた事案
最高裁で争われたホステスの源泉所得税についての判決が、先日下されました。
争点は、ホステスの支払報酬に係る源泉所得税計算の際、ホステスの報酬から差し引くことのできる控除額の計算期間の日数が、
「実際の勤務日数」か、それとも「出勤しない日も含む報酬支払い期間」か
で争われました。
最高裁は、報酬の支払い期間に応じた額とする初判断を示した上で、東京高裁の判決を破棄し、差し戻しを命じる判決を下しました。
控除金額は、勤めた日数×5,000円という計算ではなく、欠勤した日も含む報酬期間×5,000千円という判断です。
今後の税務執行にも影響を与える事案で注目されています。
第一生命の株式会社化に伴う注意点とは・・・
平成22年4月1日に、第一生命保険相互会社が相互会社から株式会社への組織変更することになり、同日付で東京証券取引所に上場することになりました。
法人・個人ともに、第一生命の保険契約者は、下記通り税務上の処理の確認が必要となります。
第一生命から、通知が来るだけでお金が動かない取引になる方もいらっしゃいますので、処理漏れが無いようご注意頂きたいと思います。
【割当てを受けた株式又は金銭に係る経済的利益の課税関係】
★法人・・・益金の額に算入
★個人・・・一時所得の収入金額
(そのほかに一時所得がなければ、50万円までは課税されません)
個人の場合、一時所得には50万円の特別控除があるため課税されることは少ないと思われますが、特に高額の保険をかけている方は御注意ください。
グループ法人税制が創設されます
100%資本関係のある企業グループの取引を原則として課税対象から外す「グループ法人税制」が2010年10月から適用される見通しです。
グループ法人税制の対象となるのは、100%グループ内の法人間の取引等で、これによりグループ内での資産や資金の移転が課税なしに行うことが可能です。
概要は下記通りです。
1.譲渡損益の繰り延べ
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の譲渡取引を行ったことにより生ずる譲渡損益について課税の繰り延べが図られ、グループ外への移転等の時に課税されることとなります。
2.寄付金
100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とし、受領法人において全額益金不算入となります。
3.中小企業の特例の制限
親会社の資本金が5億円以上の場合、その100%子法人については、資本金等の額が1億円以下の法人に係る次の制度(中小企業向け特例措置)の適用を受けることができません。
・軽減税率
・特定同族会社の特別税率の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
・欠損金の繰戻しによる還付制度
4.受取配当金の益金不算入
100%グループ内の内国法人からの受取配当について、負債利子控除を適用せず全額益金不算入とされます。
上記改正は、平成22年10月1日から適用となります。
清算所得課税の廃止に注目!
平成22年度税制改正大綱によりますと、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行する旨が明記されました。
現行の法律では、会社が解散して清算する場合、残余財産に課税法人税がされます。具体的には、解散時の資本金等の額と利益積立金額を控除した差額が清算所得として法人税が課税されます。
(その差額がプラスにならなければ法人税は課税されません)
今回の改正で清算所得課税方式は廃止され、通常の法人所得課税に移行することになります。この改正は今年10月1日以降の解散から適用されることになっています。
小規模企業共済の改正について
2010年度税制改正において、小規模企業共済制度が拡充されます。
上記制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
現行制度で加入資格があるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主または会社の役員に限られていました。
今回の改正では、個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで加入対象者を拡大することになりそうです。
上記改正により、個人事業主の事業承継が円滑に進むようになり、また共同経営者の引退後の生活保障の手助けになると思われます。