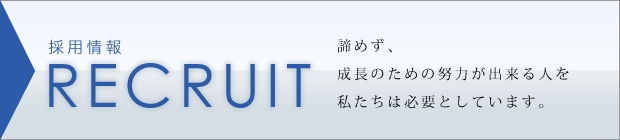最新情報WHAT'S NEW
国税不服審判所の審判官の半数が税理士等に
政府税制調査会の納税環境整備PTは国税不服審判所の審判官の半数を民間人から登用する考えを明らかにしました。
国税不服審判所の透明性を図るのが狙い。
税理士や公認会計士、弁護士の他、大学教授などから採用する見込み。
小規模宅地等の特例 二世帯住宅について
平成22年度改正で小規模宅地等の特例は、被相続人の同居親族が独立部分のある「2世帯住宅」のような共同住宅を取得する場合において、特定居住用宅地等として80%の評価減の適用を受けるには、同居親族の範囲等に留意する必要があります。
平成22年度改正では被相続人にかかる同居親族の範囲の取扱いは見直されなかった。
そして、複数の独立部分がある共同住宅で、一定の親族が同居していた者として申告があったときは、特定居住用宅地等として認める旨が通達で示されています。
措通69の4-21のなお書きによれば、被相続人とその親族が互いにプライバシーを尊重するために区分して別々に暮らす場合においても、
- 共同住宅の全部を被相続人またはその親族が所有
- 適用を受ける親族が、被相続人が相続開始の直前において居住のように供していた独立部分以外の独立部分に居住していた
- 被相続人に配偶者がいないまたは被相続人の独立部分にともに起居していた同居親族(相続人)がいない
という要件を満たせば、他の独立部分に居住していた親族が「被相続人の居住のように供されていた親族」とする申告をしていたときは、これを認めることとしています。
また、2世帯住宅の場合には、被相続人の居住していた独立部分に起居していなければ、同居親族とならりません。
し かし、同居親族として申告があったときは、同居親族が必ずしも相続税の申告期限まで被相続人の居住部分に住むことまで求めておらず、被相続人が居住してい た独立部分を相続税の申告期限まで被相続人の家財を残したままであったり、物置に使われたりしていた場合(「空家」)でも居住要件を満たすとしています。
要するに、居住継続要件については、相続人が申告期限まで被相続人の居住のように供していた独立部分に住むことまで求めているのではないようです。
eLTAXサービスが18日(木)から一時停止されます
平成22年11月18日(木)から25日(木)までの間、地方税ポータルシステム(eLTAX)サービスが一時停止されます。
上記の期間中、運用開始から5年経過を受けてシステム更改作業(ハード機器等の全面入替えやデータの移行作業)が行われます。
新システムは翌日の26日(金)8:30から利用開始となりますので、ご注意ください。
中退共の加入対象に「同居親族のみ」が追加
厚生労働省において公表されました「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案」の中で、従来同一生計親族のみを使用する事業に使用される者は 加入できなかった中小企業退職金共済が、今回の改正案で同一生計親族でも使用従属関係が認められる者については加入が認められることが明らかになりまし た。
10月17日まで省令案に対する意見が募集され、11月には省令が公布される予定になっています。来年1月1日の施行予定です。
質疑応答事例が更新
10月22日に、国税庁の「質疑応答事例」のページが更新されました。
「質疑応答事例」は、国税当局において納税者からの照会に対して回答した事例等を公開したもので、科目別に掲載されています。
今回の更新では、法人税、財産評価関係を中心に62事例が追加されました。
(新しく追加された項目にはNEWのマークがついています)
中でも「財産評価」の中には、(広大地の評価)関係で11項目が新たに追加されています。